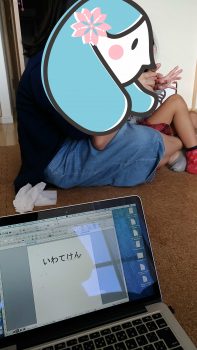いわゆる「指談」の検証は不発となりました。
しかし,多くの人が使っているとされるこの方法に対して,なぜそんな検証が必要なのでしょうか?
あえて言い切れば,「この方法は一見わかりにくく,読み取り者の意思が入っているではないかという疑惑が払拭できない」というシンプルな理由からです。
この方法によって家族で平和に暮らしているのなら,他人がどうこう言う必要はありません。
ただ,他人とのコミュニケーションなら話はちがい,客観的な方法であることが必要です。
客観性を求めるなら機器を介した方法が確かです。
しかし,機器を使った方法がうまくいかない場合も多いものです。
なので,こういった人を介した方法も必要です。
ALSの場合は「口文字」が広まりつつあります。
広義では「手話」や「ゆび文字」などもその一種でしょう。
「指談」は分かりにくい方法のため,その実効性については多くの人から疑義があります。
そう,私もそのひとり。
今回の実験協力者となる発話者は子ども(小学校4年生・障害当事者)で,障害由来により多動の傾向がみられます。
発話による会話は極めて困難な状態です。
主な読み取り者はお母さま。
日常的に指談を使っており,学校でのできごとを話すこともあるようです。
少なくともひらがなの伝達はできていると判断。
九九もできるという証言から,数字も理解していると考えられます。
ただし,先天的な障害のため,認知特性は健常児と同様ではない可能性があります。
しかしながら,認知特性が明らかでないとはいえ,指談で表現できている文字列(ひらがな・数字)は記憶できると仮定しました。
そこで,一時記憶を頼りにしたごく簡単な手順を検証方法としました。
普段使っているとされる,ひらがなおよび数字の伝達のみを行うことにしたのです。
手順は以下です。
提示文字列ごとに1と2を繰り返しました。
- 発話者(子ども)のみに対して文字列を提示する
提示文字列:いわてけん・おばけ・77 - 文字列を読み取り者(お母さま)に伝える
以上。
結果は,このようになりました。
- いわてけん → はな
- おばけ → かいじゅう
- 77 → 12
ひらがなおよび数字ともに不正解。
この結果をどう考察するか。
今は論じません。
認知特性が実験結果に影響している可能性があるからです。
そのため,指談による情報伝達が正しく行われていないとは否定できないのです。
実験方法が適切かどうか,再検討する必要があるでしょう。
つまり,エピソード記憶から言語化することで,指談により情報伝達することは行えても,文字列そのものの情報伝達は普段行わないことから,実験の意味を理解していなかった恐れがあります。
そもそも,文字列のみの一時記憶が極めて困難な可能性も捨てきれません。
その辺をきちんと検討して再実験に取り組みたいと思います。
この検証を実施するにあたって,お母さまの勇気は賞賛に値します。
この場をかりて謝意を表します。