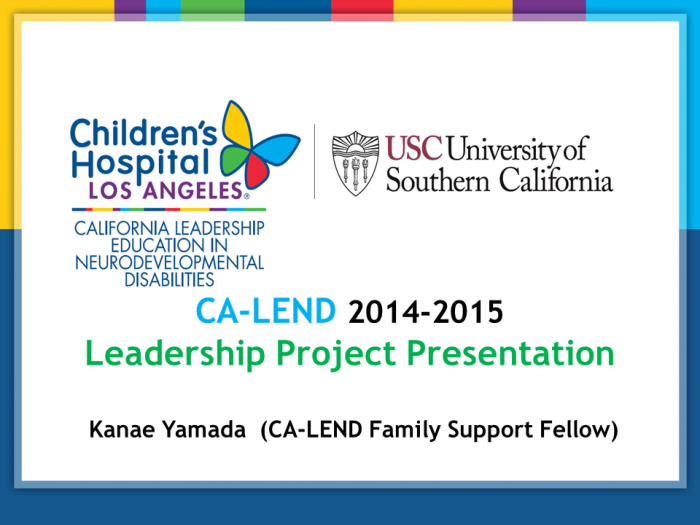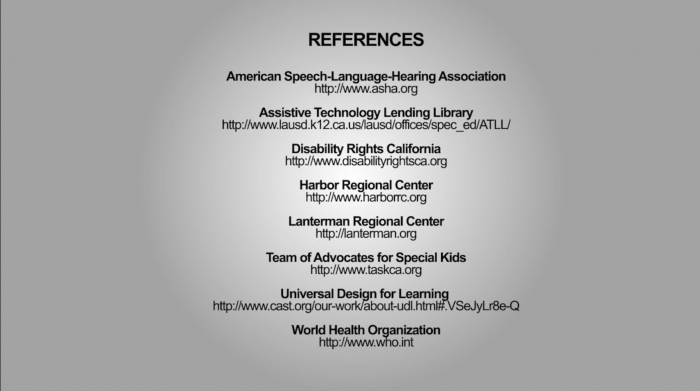これまでポランの広場では,何度か熊本の橋本紗貴さんを取り上げてきました。
ほぼ盲ろう&四肢不自由の,今年大学を卒業したばかりの女の子です。
- 謎だ!どうやって切り絵を作った?(2018年12月27日)
- 【民泊の旅】岩手の77歳の女子高生、熊本の盲ろう&車いすの女子大生、出雲国へ(2018年7月28日)
- ある美人女子大生の取扱説明書 (2018年7月11日)
- 世界でただひとり?「ブラインド視線入力」の女子大生(2017年7月13日)
- 車いす&盲ろう者でも教諭になれるはず! (2017年12月16日)
- 一見、色白のかわいい女子大生ですが、とんでもないド根性ムスメなのです(2017年9月7日)
極めて重い身体障害にも関わらず,教員を目指す姿は誰もが応援したくなるものでした。
その努力と根性がとんでもないものだったからです。
去年の試験では,教育委員会との配慮事項の行き違いにより,十分に実力が発揮できませんでした。
でも,今年は「悔いなし!」だったとのこと。
今年の本番試験後には,以下のコメントをもらいました。
教員採用試験が終わり,自分の今持っている力は出し切ったと思います。
橋本紗貴さんより(2019年7月16日)
試験を受けるまでにたくさんの壁がありました。
視覚障害 ,聴覚障害 , 肢体不自由 , その他色々な障害が重複していることで実習に行き , 試験を受け , 教員になるのは無理だと決めつける教職の先生がたくさんいらっしゃいました。
そして , 去年までの受験資格等には「介助者なしに教員としての職務が可能な者」と書いてあることで , 「あなたは(車いすで介助がいるから)教員採用試験は受けられないけど , それは知ってる?」と大学の先生から言われた時 , 悲しかったですが前に進む原動力になり , ますます教師になるという気持ちが強くなりました。
みんなと同じように試験を受けられたことは私にとって大きな一歩ですし , これから生きていく上で自信にも繋がりました。
ここにくるまでこんな私にたくさんの支援,応援 ,情報提供をしてくださった方への感謝の気持ちでいっぱいです。
試験を受けられたことがゴールではありません。
これからも前に進んでいきますので、よろしくお願いします。
なお,紗貴さんの試験前日のブログはこちらです。
まずはお疲れさま!
「介助者なしに教員としての職務が可能な者」 の条件は削除されたのは大きな追い風でしたね。
おそらくは,紗貴さんの受験例があったことから,撤廃されたのだと思います。
さらに推測すれば,受験配慮の不備を考慮すると,去年の成績はたいへんいいものだったのでしょう。
ここで,少しだけ紗貴さんの身体状態や勉強環境を取り上げてみます。
身体状況の詳しい説明は「橋本紗貴の取扱説明書」にあります。




盲ろう(視覚障害+聴覚障害)だけでもたいへん過酷な状況ですが,それに加えて肢体不自由も。。。
さらには,感覚障害もあるので,支援機器を操作するだけでも大変な労力が伴います。
支援機器の多くは紗貴さん本人が選定して使用しています。

これだけの種類の機器を使っている方が他にいるでしょうか??
しかも自分で調査して,試用して,実用時には設定も自分でこなしています。
私はこれを超える例を知りません。

人間の限界は「諦めたとき」にやってきます。
逆に言えば,諦めない限りは可能性は常にあるのです。
見えない中での視線入力。
大学の授業での自身によるノートテイクなどは,視線入力で行うそうですが,画面は見えていません。
キーボードの位置を記憶し,頭の中のイメージで入力しています。

まさかの独学点字ユーザー。
手話&触手話もやります。
よくぞ点字&手話を独学で覚えたものだと,感動せざるを得ません。
通常,点字はよほど子どもの頃からじゃないとマスターするのは困難なのです。さらに,感覚の障害があるというのに。。。
もはや,紗貴さんの学ぶ意欲を誰も止めることはできません。



大学での授業は大変!
これだけの機器がないとついていけません。
いや,これだけあっても,見えない聞こえない中では十分な情報を得るのは困難です。
手書きでの提出物はたいへんな労力を伴います。

ディスカッションがあればさらに大変です。
ちょっと特殊な機器(コミューン)を使って,補聴器越しで聞き取りできるようにしています。
紗貴さんの発話は比較的しっかりしていますが,騒々しい中では声がかき消されてしまうことも。

普通に紙の本を読むことができないため,スキャンしたものを拡大したり機械で読み上げたりしてインプットします。
ページ全体を見ることができないので,勉強の効率は大幅に落ちるのは避けられません。
活字の場合は,常に数文字単位での情報インプットです。


感覚障害等のため,書字は苦手です。余計に体力を消耗します。
本番試験では,幸いなことにパソコン対応です。

思い返せば,ある学校での教育実習の際,急きょ紙の教科書のデジタル化が必要になり,ソーシャルの力を借りて稀に見るスピードでデジタル化しました。


インターネット&SNS&Googleドキュメント(クラウド)を最大限に活用できた事例になりました。
みなさんが,普段の紗貴さんのがんばりを知っているからこその「元気玉」。
日々の生活では,お母さまをはじめ,ご兄弟による愛情深いの支援がありました。
お母さまにいたっては,体を張っての毎日の通学。
きっと,ご苦労が耐えなかったものと思います。


第三者の私からみれば,その姿は美しいものでしたが,その一言では済まない様々なことがあったことでしょう。。。
そして,今年の教員採用試験リベンジ!
本番試験のある7月14日の目前,6月初旬に教員採用試験の模擬試験が行われました。
本番試験同様の配慮で挑みました。
その結果がこちらです。

(もちろん、本人から掲載許可を得ています)
信じられない結果です。
5科目のうち3科目で1036中1位!
こんなレーダーグラフ見たことない!
どんな受験生よりも不利な身体状況の中でのこの成績。。。
紗貴さん!あんたはもう立派な先生だよ!
他に例を見ないほどの身体障害を背負って,日々の生活と受験勉強を乗り越えてきました。
私たちはその姿から学べるものが極めて多く,ここにささやかですが,紗貴さんの記録を記しました。
学ぶチカラと意欲はどんな人にも劣りませんし,誰も奪えません。
きっと,紗貴さんは着実に夢を叶えていくことでしょう。
これから,どんな人生が待っているのか楽しみですね。
私たちは,これからも紗貴さんを応援し続けます。
ちなみに,本番試験ではこのような環境で解答したとのことです。

できる限りの最大限の配慮を受けることができたのも,紗貴さんの熱意によるものでしょう。
教育委員会を動かしたのです。
おお,若干23歳で,もう世の中を変えつつあるのですね。